
20代、30代の年金はどうなるか – 将来の年金額の予想を紹介
少子高齢化が進み、将来の年金制度が破綻するかもしれないという不安の声がよく聞かれますが、実際のところ、今の若い世代の人たちは、老後に年金を受け取れるのでしょうか。今回は将来の予想される年金額を、平成26年に厚生労働省が発表した『国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し』からご紹介します。
Contents
将来の年金はゼロにはならない
将来の年金額を見る前に、年金のお金がどこから出ているのかを理解しましょう。現在の年金制度の財源は、以下の3つから成り立っています。
年金の3つの財源
- 現役世代の保険料
- 積立金
- 国庫負担
今現役で働いている人が退職した人の年金を支えているのはよく知られています。そのほか、年金の財源には今までの積立金の運用と、国庫負担があります。
少子高齢化が進み、将来年金を払う現役世代の数が少なくなることと、景気停滞で積立金が減少していることが、「将来年金がなくなる」という声の大きな原因になっています。
この仕組みを見ても分かる通り、現役世代がいる限り年金はゼロにはなりませんが、将来の年金が減額されることはほぼ間違い無いでしょう。
将来の年金額はいくらになるか
あまり知られていませんが、厚生労働省は将来の労働力の変化や景気の予想などをもとに、楽観的なものから悲観的なものまで、8パターンに渡って将来の年金水準を予想しています。
今回はその中でも、最も楽観的な予想と最も悲観的な予想を見てみましょう。
最も楽観的な予想
| 年度 | 2014年 | 2030年 | 2044年 | 2050年 |
|---|---|---|---|---|
| 夫婦の厚生年金の額(①) | 21万8,000円 | 24万7,000円 | 30万1,000円 | 34万4,000円 |
| 現役男子の平均賃金(②) | 34万8,000円 | 43万3,000円 | 59万円 | 67万5,000円 |
| 所得代替率(①÷②) | 62.7% | 57.2% | 50.9% | 50.9% |
ここでは、夫が平均的なサラリーマンで、妻が専業主婦の場合の夫婦の厚生年金額の推移を紹介しています。
経済が成長していくと、厚生年金の額、平均賃金ともに上がっていくのでイメージしにくいですが、将来の年金額で大切なのは、一番最後の所得代替率です。
これは、年金が現役世代のどれぐらいの割合支給されるのかを表す指標です。
例えば、2014年時点では、厚生年金の額が21万8,000円で、現役世代の賃金が34万8,000円なので、年金で生活している人は一般的な現役世代の方の賃金の62.7%のお金を受け取っている、ということです。
これが2050年には50.9%と予想されているわけですから、今年金で生活している人たちの水準より2割ぐらい少ない年金が支給される、ということになります。
もっと具体的に言うと、今の時代で考えた場合、年金の水準が現在の21万8,000円から16万5,000円ほどに減っているイメージです。
次に、国が考える最も悲観的な予想を見てみましょう。
最も悲観的な予想
| 年度 | 2014年 | 2030年 | 2036年 | 2055年 |
|---|---|---|---|---|
| 夫婦の厚生年金の額(①) | 21万8,000円 | 20万7,000円 | 20万円 | 17万8,000円 |
| 現役男子の平均賃金(②) | 34万8,000円 | 38万4,000円 | 40万円 | 45万6,000円 |
| 所得代替率(①÷②) | 62.7% | 53.8% | 50% | 39% |
この予想では、2055年に、最初にご紹介した年金の財源である保険料、積立金、国庫負担のうち、積立金が枯渇してしまいます。
つまり、完全に現役世代の保険料と国の税金で年金を負担することになります。
このケースでは2055年には所得代替率が39%になっています。これは現在の年金受給額より約4割弱少ない水準です。
こちらを今の物価水準に直すと、現在の21万8,000円から13万6,000円に減っているイメージです。
2055年の予想ということは、ちょうど今30才前後の人の年金額に当てはまります。
年金も自助努力が必要な時代へ
今回は将来の年金の予想をご紹介しましたが、いかがでしたか?
うまくいけば今の水準より2割減、最悪の場合は4割弱(38%)減になる予想で、「やっぱり将来年金は減るのか」とがっかりした方や、「それでも思ったよりはもらえそう」と安心した方、さまざまだったと思います。
大切なのは、年金の予想額がわかれば、対策を立てることもできるということです。将来年金がなくなるなら、いくら貯金すればいいのかわからないという人でも、将来の年金は2~4割減りそうと分かると、それなりの対策を立てることができます。
NISA、iDeCo、つみたてNISAなど最近さまざまな制度ができていますが、これらは老後資金を貯めるという目的であれば、税制面で非常にお得な制度です。ただし、自分で手続きしなければ加入できません。
現役時代に一生懸命働けば、何もしなくても年金で暮らせた時代は終わり、これからは自分の知識と努力で老後に備える必要がある時代になっていきます。上記の制度ができた理由は、つまりは「老後のための制度はいくつか作ったので、2~4割の減額分はそれを利用してうまく埋め合わせてください」というメッセージです。
20代30代は老後のことと言われてもピンと来ないと思いますが、将来の年金額の減額が大きい若い世代こそ、老後の備えを早めに始めましょう。

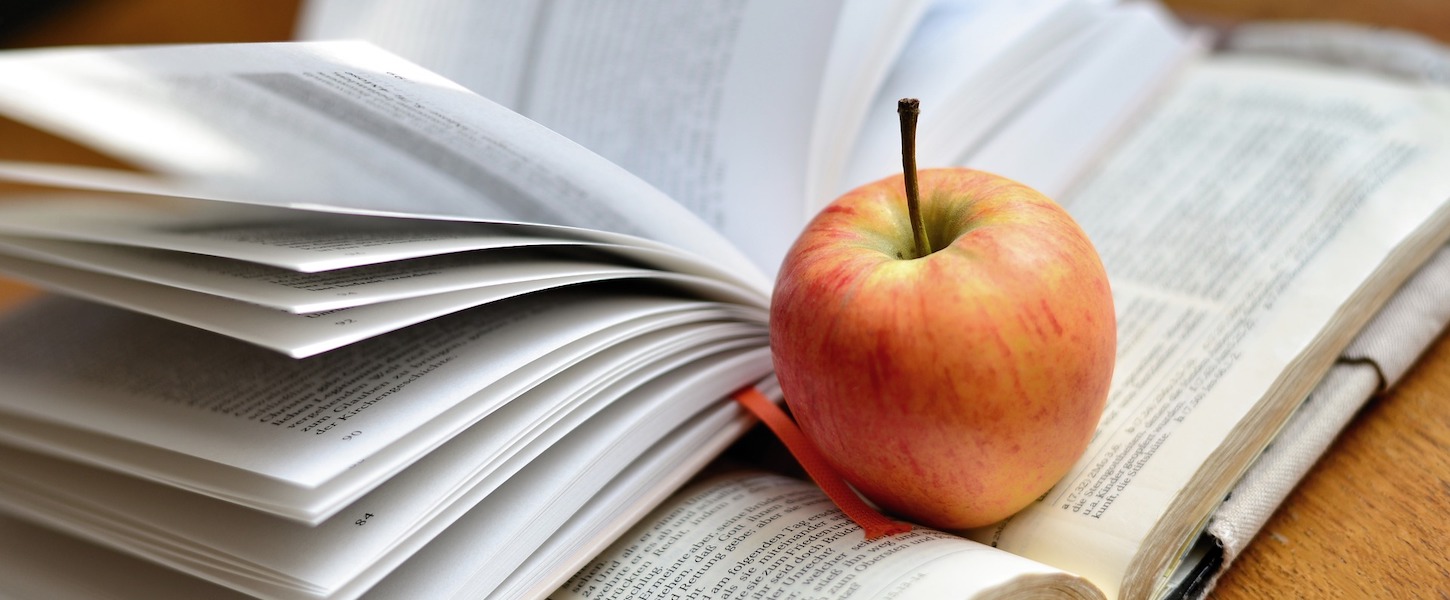






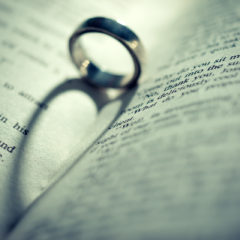


この記事へのコメントはありません。