
自営業者が利用できる老後資産形成のための制度(下)
前回のコラム、「自営業者が利用できる老後資産形成のための制度(上)」では、自営業者が加入できる年金・退職金制度をご紹介しましたが、今回は具体的にどれを利用すればいいのかと、私が利用している制度をご紹介します。国民年金基金とiDeCo、どちらを使うのかが主なテーマになります。
Contents
1. 国民年金基金とiDeCo、どちらを選ぶか?
国民年金基金は確定給付、つまり加入時点で将来の受給年金がわかる制度だと紹介しましたが、1991年の制度開始時では、その予定利率は5.5%でした。2002年でも3%以上ありましたが、2016年時点で1.5%となり、非常に低い水準となっています。
また、急激な予定利率の下がり方からもわかる通り、昔の予定利率が財政を圧迫し、今後さらに予定利率が下がるか、下手をすると予定利率が高い時代に加入した方の利率も下がる可能性があります。
かたや、iDeCoにも元本確保型の商品はありますが、制度を利用するには年間2,000円から7,000円の管理手数料がかかります。
所得控除というメリットはありますが、もしどうしても損をするのが嫌で、iDeCoに加入しても元本確保型しか買いたくない問いのであれば、将来予定利率が下がるのが前提でも、手数料無料の国民年金基金に加入するのも一つの手です。
結論から言うと、
- 元本が減るリスクを取りたくない人で、国の財政を信用できる人は国民年金基金
- 投資信託などで長期にわたって運用したい、または国が信用できない人はiDeCo
を選ぶことになりそうです。
ただし、国民年金基金に加入すると、わずかな額ですが付加保険料が納められないのは、ご紹介した通りです。
2. 年金資産形成の一案
ここで、私がどのように制度を利用しているのかをご紹介します。
まず、最初に加入したのが、付加保険料です。少額とはいえ、リターン率を考えた場合、この制度は真っ先に入っておきたい制度でした。各自治体の市役所、もしくは区役所の国民年金係で申し出れば、すぐに加入できます。
次に加入したのが、小規模企業共済でした。この制度は国民年金基金やiDeCoに比べ、少額から加入できる(1,000円から)、いざという時事業資金を借りれるという点で優れています。商工会議所などで加入できるそうですが、銀行でも加入できます。私も銀行で加入手続きをしました。
最後に加入を検討しているのが、iDeCoです。現在はまだ加入していませんが、私の場合付加保険料を納付しているため、国民年金基金という選択肢がなく、自動的に年金の増額を求めるならiDeCoを選ぶことになります。iDeCoは加入する金融機関を自分で選び、選んだ金融機関のコールセンターかwebから資料請求することで申し込むことができます。
老後資産形成と税金軽減のメリットの大きさ
では、この3つの制度を利用した場合、どのようなメリットがあるかを見ていきましょう。
個人事業主の方の、現在の課税所得が500万円とすると、所得税は、57万2,000円です。 ・・・ ①
この方が、今から付加保険料400円、小規模企業共済7万円、iDeCo6万7,000円とそれぞれ満額まで加入するとします。年間の掛金は、
(400円 + 7万円 + 6万7,000円)× 12ヶ月 = 164万8,800円
となり、これらの掛金は全額が所得控除されるので、課税所得は、
500万 – 164万8,800円 = 335万1,200円
になり、この場合の所得税は、24万2,000円になります。 ・・・ ②
つまり、①と②の差額分、32万円の税金が軽減されます。単純にこの額だけ手取りが増えると考えてもらえばわかりやすいでしょう。
もちろん年間165万円を老後資金に回すということなので、生活に使えるお金は少なくなりますが、軽減される税額を考えると、165万円-32万円の実質133万円で、165万円分の老後の備えができると考えると、随分有利な制度とおわかりいただけるのではないでしょうか?
上記の計算は所得税だけの値ですが、実際は住民税も軽減されるので、税金の減額はより大きくなります。
まとめ
今回は自営業者が利用できる年金・退職金制度をご紹介しましたが、これらは自分で手続きをしないと利用できないものばかりで、その辺りが会社が老後の面倒をみてくれる会社員の方とは違うところです。
収入やお子さんの数、生活費によって、どれも満額まで加入できないかもしれませんが、生活が苦しくならない程度に少額からでも加入しておけば、とてもメリットがある制度になっていますので、まだ加入していない人は是非検討してみて下さい。

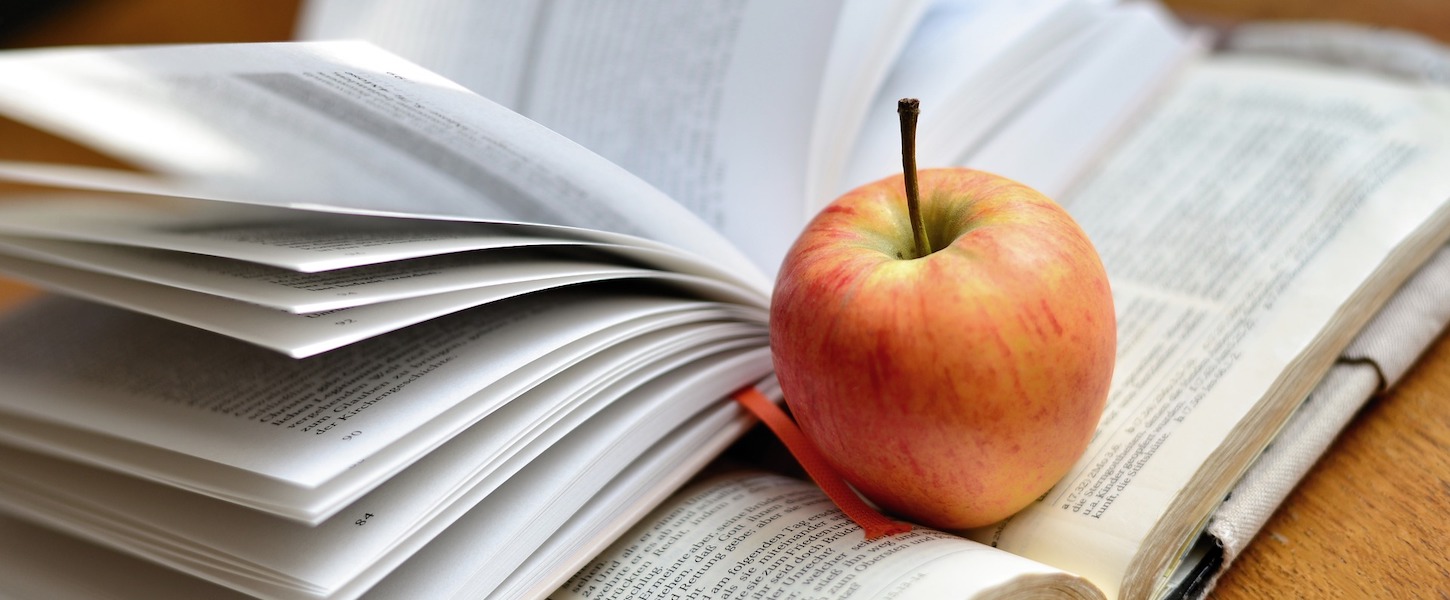





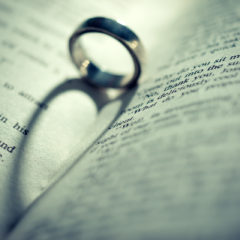


この記事へのコメントはありません。